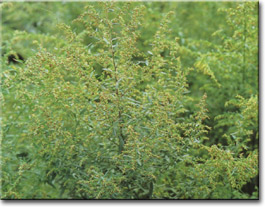花粉症とは?
花粉症とは植物の花粉によって引き起こされるアレルギー性の病気です。

花粉症を引き起こすのは体外から進入する花粉を、有害な物質として排除しようとする反応が過剰に起こるためです。
このような過剰な反応を起こしやすい体質をアレルギー体質と呼び、生まれつき決まっています。
このため空中に飛んでいる花粉を同じように吸い込んでいても、花粉症になる人と、ならない人がいます。
代表的なイネ科植物
花粉症と言えば春に生じる 「スギ」 「ヒノキ」 の花粉を思い浮かべますが、秋にも花粉症を生じる植物があります。
その主な植物について説明します。
A ブタクサ(キク科)

道端や空き地でよく見られる黄色い花をつけた植物です。
9月の上旬から10月の下旬にかけて花粉が飛散します。
スギ花粉と比べて広範囲には飛散しませんが、日本の3大花粉症のひとつとされ、秋の花粉症の代表的な原因物質です。
北アメリカ原産で、アメリカでは花粉症の原因としてもっとも注意されています。
ちなみに1961年に日本で報告された花粉症第1号です。
B アキノキリンソウ(キク科)

日当たりの良い道端や土手に見られる多年草の植物です。
花がキリンソウに似ているので、秋に咲くキリンソウの意味で名づけられました。
花の形が盛り上がるお酒の泡に見ていることから、別名「アワダチソウ」とも呼ばれています。
10月上旬から11月下旬にかけて花粉が飛散します。
C ヨモギ(キク科)
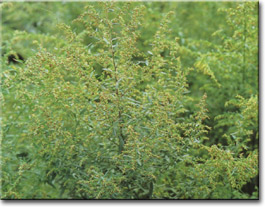
荒れ地や土手、畑などに見られる香りある多年草の植物で、茎は高さ1m。
葉は楕円形または卵形をしていて繁殖力があります。
9月の下旬から10月の中旬にかけて花粉が飛散します。
アレルギーの原因のとなる強さはブタクサ以上で、花粉の量も増加傾向にあり、患者数も増えています。
キクの花粉と共通する部分があり、「ヨモギ花粉症」と診断された場合は「キク」にも注意が必要です。